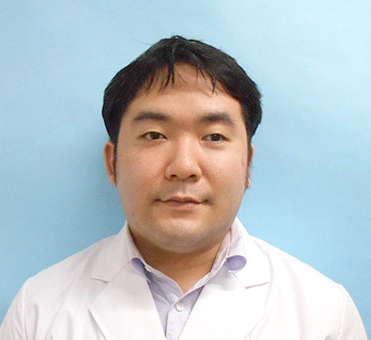小児科のかかり方
小児科外来は午前の一般外来と午後の専門外来に分かれています。
一般外来は紹介外来制ですので、初診の方は必ず紹介状(診療情報提供書)をお持ちください。
当院の近くには小児科を専門とした先生が多く開業されていますので、かかりつけ医を持つことをお勧めいたします。体調が悪くなった時や心配なことがある時は、まずかかりつけの先生にご相談ください。詳しい検査や入院が必要と判断された際に当科へご紹介いただくことになります。
診察後に再診が必要と判断した際には、担当医やスタッフが次回の外来予約をお取りします。受診の間隔が開いているなどで予約が入っていない場合は、小児科外来までご連絡を下さいますようお願いいたします。
専門外来(午後診療各種外来)[予約制]
午後の外来は専門的な診療を行います。
すでに診断がついている患者さんで当院への転院をご希望される場合は、それまで通院していた病院の紹介状(診療情報提供書)をお持ちください。予約制ですのであらかじめ小児科外来へ連絡をお願いいたします。
まだ診断がなされていない患者さんは、まずは午前の一般外来で総合的に診療を行い、適切な対応方法を検討いたします。その後に必要に応じて専門外来のご案内をいたします。
| 予防接種 |
水曜日 |
重度のアレルギーや慢性の病気のために開業の先生の元では、予防接種を受けることが難しい方にワクチン接種を行います。
対象となる患者さんにはRSウイルス感染症予防のシナジスの接種も行っています。 |
| 乳児健診 |
担当医 |
当院で出生された乳幼児を中心に健診を行っていますが、保健センターや開業の先生からの紹介患者さんも来院されています。 |
| アレルギー外来 |
水曜日 |
気管支喘息、食物アレルギーなどの患者さんの専門外来です。アナフィラキシーを起こした方用のエピペンの処方も行っています。 |
| 腎臓外来 |
月1回
木曜日・月曜日
午後不定期 |
慢性腎炎やネフローゼ症候群、夜尿症などの患者さんを診療しています。学校検尿で異常を指摘された方のうち、専門的な診療が必要と判断された方の診療も行います。 |
| 心臓外来 |
火曜日 |
先天性心疾患で内科的治療が必要な患者さんや川崎病の既往のある患者さんを主に診療しています。学校の心臓検診で異常を指摘された方のうち、専門的な診療が必要と判断された方の診察も行います。 |
| 内分泌外来 |
水曜日 |
小児の肥満や糖尿病、低身長や思春期の異常、甲状腺の異常などホルモンの病気の患者さんを診療しています。 |
| 神経外来 |
木曜日 |
てんかんや全身性の病気に伴う神経症状のある患者さんなどを診療しています。 |
| 小児外科外来 |
木曜日 |
停留精巣や陰嚢水腫、ヘルニアなどの小児外科疾患を対象に、順天堂大学医学部附属順天堂医院小児外科と連携して診療をしています。
詳しくはこちらをご参照ください。 |
| 発達外来 |
水曜日 |
幼児から小学生を対象として、発達に心配のあるお子さんの診療をしています。 |
| 2週間健診 |
金曜日 |
出生後2週間(産婦人科病棟を退院して1週間)頃を目安に健診をおこなっています。
詳しくはこちら(PDF)をご参照ください。 |
※海外旅行に伴うワクチン接種は、年齢を問わずご相談に応じます(国内で承認されていないワクチンの接種は行っておりません)。
小児科のご案内
特長
小児科は「小児の総合医」ですので、子どもの内科的疾患の全てを診療いたします。
新生児から中学生までの患者さんが診療の対象ですが、小児期に発症した慢性の病気をお持ちで、高校生や成人になった患者さんもたくさん通院されています。急性疾患や慢性疾患の急性期の診療を主に行なっていますが、子どもの病気に関することならば、何でもご相談に応じます。中にはより専門性の高い施設での診療を受けた方が良い場合もありますので、その際には責任を持って最善の病院を紹介いたします。
学会認定施設
日本小児科学会:専門医研修施設
小児外科のご案内
小児外科外来(第2木曜日 午後[予約制])
担当医:山髙 篤行
順天堂大学医学部小児外科 山髙篤行特任教授が診療を行います。外科的治療が必要な場合には、順天堂大学医学部附属順天堂医院や関連病院で手術等の治療を行います。その後の診療は、当院あるいはかかりつけ医で受けることができますので、ご自宅の近くで継続した診療が受けられます。
主な対象疾患
| 鼠径ヘルニア |
臍ヘルニア |
陰嚢水腫 |
| 停留精巣 |
包茎 |
埋没陰茎 |
| 尿道下裂 |
水腎症 |
膀胱尿管逆流症 |
| 腹痛・虫垂炎 |
副耳 |
|
上記の一般的な小児外科疾患・小児泌尿器疾患のほかにも、胎児診断症例、新生児の外科的疾患にも対応いたします。
※検査等により緊急手術の必要性がある疾患であった場合、関連施設である順天堂医院小児外科・小児泌尿生殖外科へのご紹介も行います。
対象年齢
原則として、初診時は赤ちゃんから中学生までを対象としています。
なお、小児期に小児外科で手術を受けた患者さんで、高校生や成人になった方も通院されています。
受診について
まずは紹介状(診療情報提供書)をお持ちのうえ、午前中の小児科外来を受診してください。小児外科外来の予約をお取りするとともに、あらかじめ検査が必要かを判断いたします。検査が必要な場合は、検査を行った後での受診となります。
小児病棟について
(新型コロナウイルス対策と、その後の病院診療体制の調整のために随時変更があります。)
一般小児病床と新生児病床があり、主に急性疾患で入院が必要な子どもたちの診療を行っています。
一般病床では原則としてご家族の付き添いは不要ですが、ご家族の希望あるいは治療上必要な場合には、付き添いをしていただく場合もあります。面会時間は午前8時から午後8時と長く設定してありますので、お子さんが入院された際には、お仕事やご家族の都合に合わせて来院ください。もちろん面会時間を通して付き添われる方もいらっしゃいます。
病棟には子ども療養支援士や保育士をおいて、入院中の子どもたちのストレスを少しでも軽減できるように努めています。
子ども療養支援士について
「子ども療養支援士」をご存知ですか?
医療を受ける子どもたちの不安に寄り添い、気持ちの緩和やストレスの軽減など心理的ケアを行うスペシャリストです。
子どもであっても自分が受ける医療を分かることは、病気に立ち向かうパワーにつながります。
たとえば採血検査では、「こわい」「いたい」という不安を受け止めて、それぞれの子どもたちに合わせ、ぬいぐるみや写真、ときには本物の医療器具を使って説明し、乗り越える方法を考えます。ゴロンと寝転がって受けるか、座って受けるかDVDを観ながら受けるかなど、“一緒に決める”ことがポイントです。
子どもが納得し処置を終えると、「できた!」「がんばった!」という気持ちに繋がります。



キラリ!子ども療養支援士のご紹介
当院には2名の子ども療養支援士が活躍しています。共通の思いは“子どもたちを病院嫌いにさせないこと”。
病気と戦っている子どもたちの強い味方です!
「病院」とはどんなイメージですか?
病院には、子どもたちのことを大切に思う人がたくさんいて、体調が悪いときやけがをしたときに治してくれます。それでも、何をするかがわからないことは恐怖であり、子どもたちも「知りたい」と考えています。
私たちは遊びをとおして、病院にいても子どもたちがその子どもらしく過ごせる時間を大切にしています。子どもたちが意見を尊重されていると感じ、スタッフと信頼関係が築けたとき、処置や検査で子どもの力が発揮されるのではないでしょうか。
病院が子どもにとってやさしい環境になるように、がんばって活動しています。お家ででも病院とはどんなところか、一度お話してみてください。
子ども療養支援士 藤川・橋本
在宅医療について
当院小児科では、在宅での人工呼吸療法・酸素療法・胃ろう管理などを実施しています。当院の医師と訪問看護師による訪問診療を定期的に実施していますので、短期間入所や病状悪化時の入院を除いて、患者さんが来院する必要はありません。
当院に併設されている訪問看護ステーションは歴史も長く、多くのノウハウを持ち、きめ細かな対応を行なっているのが特色です。近隣にお住まいで在宅医療への移行をお考えの方は、事前に当科へご相談いただくことをお勧めします。
また、当院は2009年(平成21年)10月より、埼玉県の重症心身障害児短期入所事業に協力しています。当科では超重症児の短期入所にも対応しています。
埼玉県内の小児在宅医療に対応可能な医療施設等については以下をご参照ください(外部サイトが開きます)。
在宅医療の必要な小児患者さんを当院へご紹介していただく医療機関の方へ
他の施設に入院中で自宅が当院に近い小児患者さんの在宅医療への移行をご検討されている際には、ぜひ当科へご相談ください。地域によって提供可能な医療サービスはさまざまですので、在宅医療に必要な医療福祉資源については、実際に在宅医療を受ける地域で調整するのが良いと考えます。
初めに患者さんに当院へ転院していただき、当院で在宅医療の調整を行うことをお勧めいたします。当院からの距離により、お引き受けできる住所には限りがありますが、ご相談いただければ極力調整をいたします。
また、小児の悪性腫瘍などの自宅での看取りにも対応いたします。
当院周辺の「放課後等デイサービス」について
当院周辺の肢体不自由の対応、または相談が可能なデイサービス施設です。
「放課後等デイサービス」は、障がいのある子どもへの療育の場、居場所の役割とともに、家族に代わって一時的なケアを行うことで日々の疲れを取ってもらう「レスパイトケア」としての役割も担っています。
| 診療所名 |
住所 |
概要 |
リンク |
| らいおんハート遊びリテーション児童デイ西川口 |
埼玉県川口市並木2-31-3 |
PDF |
ホームページ |
| アトリエ・ユリシス・デイ |
埼玉県川口市大字芝4583-6 |
PDF |
ホームページ |
| 放課後等デイサービスやまぶき |
埼玉県川口市朝日6-22-16 |
PDF |
– |
| おれんじキッズ&児童デイサービス・アニマート |
埼玉県川口市戸塚2-2-14 モアニケアラ101 |
PDF |
ホームページ |
| 児童発達支援・放課後等デイサービスgreen room |
埼玉県川口市里573-1 |
PDF |
ホームページ |
| 児童発達支援事業所グランアーブル |
埼玉県戸田市中町1-6-6 |
PDF |
ホームページ |
※上記は掲載をご了承いただいている施設となります。
※提供できるサービスが変わることがありますので、詳細は各施設
訪問歯科診療について
身体が不自由なため通院が困難なお子さんの歯科診療については、川口歯科医師会にて訪問歯科診療を行っています。
詳しくは下記をご参照ください(外部サイトが開きます)。
実績
診療実績
| |
2024年 |
| 入院患者実数 |
1,151 人 |
| 新生児入院実数 |
227 人 |
| 外来患者総数 |
14,541 人 |
小児健康教室
ぜんそく・アトピー性皮膚炎・腎臓病・けいれん・肥満などの慢性の病気を持つお子さんたちが、病気に負けることなく、健やかな日常生活や学校生活を送れるようにと願い、定期的にWEB配信で開催しています。
それぞれの病気について、どのような症状や種類があるのか、治療を行う場合にはどのような方法があり、その効果や副作用はどうなのか、その病気が将来どうなっていくのかなどについて、保護者の方にわかりやすく解説しています。
家庭生活での注意点はもちろん、保育園や幼稚園、学校などで気をつけることなども具体的に解説しています。
当院に通院されている患者さんやそのご家族はもちろん、保育園や幼稚園の先生方など、どなたでもご参加いただけます。
参加された皆さまからのご質問(2025年度開催分)
赤ちゃんの話
スクリーンタイムの影響についてなのですが、言葉のやり取りが苦手、人との関わりに感心がないなど具体的な変化は見られるのでしょうか。また、保育の現場でできる、影響を和らげる関わりはありますでしょうか。
乳幼児のスクリーンタイム(ST)が長いほど、言語機能領域の遅延を生じやすくなるとは言われていますが、それ以外の領域(社会性、運動機能など)や神経発達を阻害するというエビデンスまではまだないようです。STが子供に望ましくない影響を与えるのは、STにより外遊びの時間が制限するからとも言われています。従って、外遊びの時間を増やすことはとても良いと言われています。外遊び、特に全身を使って自然に触れる遊びは、神経発達の促進、認知機能やメンタルヘルスの向上にも繋がるというエビデンスがあります。また神経発達症の子供たちが、よりデジタル視聴に惹かれ、恩恵をうけることがあるかもしれないと考えられています。
(小児科 西﨑)
予防接種について安全性など、さまざまな議論がされる世の中になったと感じているが保護者の方が安心し納得できる伝え方はあるか。
指示的な態度で説得を試みても相手が受け入れ、実際の接種に結びつく可能性は低いと考えられています。アプローチの方法として、「動機づけ面接」と言う方法があります。まず、具体的に何に不安を感じているのかを聞き、相手の考えに対し肯定的に答え共感を示します。そこからは相手の質問を聞き返しながら、都度説明を行ない、最後に要約を行います。要約まで聞くことで、私たちが自分の話を注意深く聞き、熟慮していることを実感できます。押しつけや説得ではうまくいかず、相手の意見を追従するだけでも解決には至りません。ワクチン接種をする人たちが、自主的に接種を検討するための動機づけをすることが求められます。難しいですが。
(小児科 西﨑)
現在レトルトやフリーズドライの離乳食が増えている中で、それらもはじめての食材を試したことにしてもよいのか。
「レトルトやフリーズドライの離乳食が食べられた」ということであれば、その食材に対してある程度の耐性はあると考えられます。しかし、商品によって含まれるたんぱく質(アレルゲン)の含有量は違うため、少量ずつ試す事をお勧めします。
(管理栄養士)
食物アレルギー
卵殻カルシウムの入ったお菓子は卵アレルギーを持つこどもが食べても問題無いのでしょうか?
卵殻カルシウムは菓子類に使用されることが多いですが、ほとんど卵タンパク質を含まないため、摂取可能とガイドラインで記載されています。なので、卵殻カルシウムは原則除去不要(食べて良い)とされており、私自身の実際の診療でも、卵殻カルシウムが原因で症状が出たと思われる症例を経験したことはありません。
(小児科 内藤)
アレルギー反応について、私は成人後に症状が見られました。本研修の中で花粉症によるアレルギーは女性の方が多いと性別による差異が見られるとのことでしたが、年齢によっても変わってくるのか、子どもでも同じように急に発症することがあるのかが疑問に感じた部分です。(質問のみ掲載しました。)
いわゆる花粉症は若干女性に多く、年齢としては10~30代での発症が多いようです。花粉-食物アレルギー症候群(花粉症をもっていて、かつ、果物や生野菜、豆類などで主として口腔の症状がでる方)は、小学校で0.99%、中学校で2.75%というデータがありますので、年齢が進むにつれて急に症状が出ることがあります。
(小児科 内藤)
夜尿症
夜尿症の治療について、直接済生会様へご相談することは可能でしょうか?紹介状による受診からとかになりますでしょうか?
当院へ受診をご希望の場合には、かかりつけ医を受診し、腎臓外来宛の紹介状を作成して頂いてください。
その後、お電話で(0570-08-1551)予約をお取りください。よろしくお願いいたします。
けいれん
以前、病児保育でけいれん持ちのお子さまをお預かりした際に、ダイアップを持参していただいたのですが、ダイアップの処方箋に「けいれん発作時に使用」「けいれんを抑える薬」と表記してあり、処方された病院の医師に使用方法を確認しても、「けいれん発作時に使用で」との返答でした。元々把握していた知識としては、こちらの研修と同じ解釈だったのですが、小児科によっては違う処方や用途になったりするものなのでしょうか…?
ご質問ありがとうございました。
ダイアップが「今起きている発作を速やかに止めることができる」との報告(調査結果)は、いくら探しても見つかりません。しかも、薬理学的にみても発作をすぐ止めることはできないはずなのです。
しかし「発作が起きたらダイアップを入れてね」と指示する医師は時々います。
背景には、以下の流れがあると思います。
以前は発作が起きた時に家庭や園などでできる治療がありませんでした。
ダイアップが発売されてしばらくは、「ダメ元かもしれないが、何もしないよりは…」とか「すぐに効かなくても20-30分後に効いてくれれば重積を阻止できるかも…」と考えて、発作が起きたらダイアップを使っていました。
けいれんはたいてい5分以内に止まり、ダイアップを使用してもしなくても経過は変わらないことがほとんどなので、(効果が望めない方法だったとしても)患者さんに不利益はありません。そのために医師の指示が問題になることもほとんどありません。
よって、この時の考え方から抜けられない医師も多く、「発作が起きたらダイアップ」となるのです。
なお、以下のような場合も稀にあります。
発作時にダイアップを使うと、数分以内に発作が止まることが多いです。動画をご覧になった方であれば、これは「使わなくても止まったのでは」とご理解頂けたかと思います。これを「ダイアップが効いた」と考える残念な医師がいます。
ご指示を頂いた医師が前者でありますように。
(小児科 有井)
参加された皆さまからのご質問(2024年度開催分)
けいれん
保育園での対処方法も教えていただければと思います。
保育園での対処方法も基本的には家庭と一緒です。まずは大きな怪我がないかを確認してください。大丈夫そうなら、安全な場所で丁寧に観察してください。初回の発作は(原因が分からないので)救急要請が現実的でしょう。すでに診断がついていて、いつも通りの発作ならそのまま見守ります。発作が長い(初期設定は「5分以上」発作が続くとき)、断続的に繰り返し発作が起きる、などの場合は同様に救急要請をしてください。
(小児科 有井)
ぜんそく
子どもが喘息があるのですが薬を減らすタイミングはどの位の期間発作がなかったら減らしても大丈夫ですか?
目安としては、3ヶ月以上、喘息の発作がなければ治療を軽くしていくことを検討するとされています。ただし、発作が起きやすい季節に薬を減らすのは危険であったり、もともとの重症度にもよるため、減らす場合はよく相談して頂いた方が良いと思います。
(小児科 内藤)
参加された皆さまからのご質問(2023年度開催分)
夜尿症
小学校低学年で膀胱容量が正常で、夜尿量も100mL以下(おむつの重さ30-80g)の場合の治療はどうなりますか?週5回以上の夜尿でも、夜尿量が多くないのでまだ積極的治療はしなくて良いのか教えて欲しいです(通っている病院では一年生なので便秘のコントロールのみで積極的治療はしてもらえません)。
小学生低学年でも、頻回の夜尿(週4日以上)が持続しているなら、生活指導や便秘治療に加えて、積極的治療(薬物療法、アラーム療法)の適応はあると思います。夜尿量が少ないタイプは、薬物療法(デスモプレシン)が効きにくい可能性がありますので、アラーム療法を検討してよいと思います。夜尿日誌をつけていただき、夜尿量(重くなったオムツ重量測定)と起床時第一尿量の合計が多い(体重の7倍以上)ならば、デスモプレシンとアラーム療法の併用する場合もあります。ご紹介いただければ、腎臓外来で拝見させていただきますので、よろしくお願いいたします。
(小児科 藤永)
参加された皆さまからのご質問(2022年度開催分)
音楽療法
済生会の小児病棟でも定期的に開催してもらえますか?
小児病棟は入院環境となりますし、感染対策や療養中の患児もいることから行っておりません。なお、来年度も動画配信を予定しています。スケジュールにつきましては当院ホームページおよび小児科外来・関係各所に配布していますので、そちらでご確認ください(スケジュールの公開および発送は来年3月~4月ごろを予定しています)。
(小児健康教室担当)
すてきな講座を無料で見られて感謝です。音楽療法について、関心があります。学ぶための機会を捜している所でしたが高額なお金がかかるようで、とん挫してました。小学校の通常クラスにも、共通行動がとれず、気持ちが荒れてしまいがちな子も多くみます。心理的なアプローチからの知識が欲しいです。ぜひ次の講座の情報をいただきたいです。
来年度も動画配信を予定しています。スケジュールにつきましては当院ホームぺージおよび小児科外来・関係各所に配布していますので、そちらでご確認ください。(スケジュールの公開および発送は来年3月~4月ごろを予定しています)。
(小児健康教室担当)
発達障害の児童に対する保健室での実践例やおすすめの実践方法を知りたいです。
実践例につきましては、今後の「発達障がい児への音楽療法」でお話をさせて頂きたいと存じます。
(市田)
歩行訓練で呼吸に合わせてテンポをとるという事ですが、呼吸回数は1分間に20~30回と遅いので、その中で具体的にどのように合わせているのか知りたいです。
実際に行う際は患児の様子に合わせていますので、具体的にお話するのは難しいのですが、理学療法士と歩行訓練をしている場合は、まずは、どのようなテンポで歩いているのかを少し観察を致します。
(市田)
夜尿症
小1の息子のおねしょで悩んでいます。まずは生活改善したいのですが、共働きで帰りも遅く、まずはお風呂、その後20時頃から20時30分まで夕食、22時頃の就寝となりますので、飲水2時間空けることが難しい状況です。この場合、薬物もしくはアラーム療法に直接進められるのでしょうか?
基本的には、夕食後から就寝までは2時間の水分制限(200mL)が守れないと夜尿の早期改善は厳しいかもしれません。
抗利尿薬(デスモプレシン)は2時間の水分制限ができない場合は使用できません。
可能な範囲で夕食の塩分や乳製品を控えたり、積極的治療を希望されるならばアラーム療法がよいと思われます。
(小児科 藤永)
保護者からおねしょについて相談を受けた時に、就学前のお子さんでも受診も1つの手段であると伝えて良いのですか?
5歳以上で月に1回以上の夜間の尿漏れが3か月持続する状態のことを夜尿症と定義されています。
したがって、5歳以上で夜尿に悩んでいる場合は、一度、小児科を受診しても良いと思われます。
薬物療法やアラーム療法といった積極的治療は小学校に入ってから(6歳以上)にはなりますが、生活指導のみで夜尿が改善することもあります。
(小児科 藤永)
小3の娘で、夜尿症ではないのですが、1年以上、寝る前に何回かトイレに行き、夜中も1回は起きているようです。 昼間はトイレの回数は多い方ではないですし、飲む量もそんなに多い方ではありません。 1回ぐらいでは問題ないのでしょうか?また、睡眠に影響があるのではないかと思っているのですが、どこに相談すれば良いのでしょうか?
多くは朝まで蓄尿力がつくことで夜尿が消失しますが、まれに覚醒排尿できるようになって夜尿が消失する小児もいます。
しかし、1年前から急に夜間覚醒をするようになったのであれば、非常に稀ですが、多尿になるような器質的疾患(尿崩症、糖尿病など)を発症した可能性があるので、一度、小児科を受診したほうが良いと思います。
(小児科 藤永)
ぜんそく
3歳の息子がおります。 風邪をひいて咳がひどく、その際にベネトリン吸入薬、テオフィリン、メプチンなど動画で紹介されていた薬が処方されていました。 主人は小児アトピーで喘息でした。息子も喘息でかかかりつけの先生に聞いたところ、風邪をひいた時に喘息みたいになるんでしょうね。風邪を予防して下さいと言われました。 幼稚園に行き始めたばかりで風邪を引かないのは無理です。大発作が起こらない限り、喘息という診断はされないのでしょうか。大発作を予防する為に、予防薬を処方して頂くことは推奨されてないのでしょうか。 宜しくお願い致します。
「乳幼児喘息」と確定診断するには、発作の大きさではないので、大発作をおこしたことがないと診断されないというわけではありません。
明らかな息を吐くときの喘鳴が聞かれる機会が3回程度あること、吸入薬への反応性、その他の疾患でないこと、家族歴等から総合的に診断します。
実際には、ご質問者さんのパターンのように、幼稚園に行き初めて風邪(呼吸器感染)のたびに咳が多かったり、時に喘鳴が聞かれる方は多くいらっしゃいますし、その中に喘息の患者さんが存在していることも確かです。逆に言えば、感染がない(熱や鼻汁などない)にもかかわらず喘鳴が聞かれることがあれば、喘息である可能性が高くなります。「風邪をひいたときに咳があり、喘息に準じた治療薬を処方される」とのことですので、恐らくまだ喘息とははっきり診断されないものの、可能性がある状態だろうと推察します。あとは、学童まで繰り返すようであれば採血や呼吸機能検査なども診断の参考にもなりますので、長い目で見ていくしかないかと思います。
予防に関してですが、確かに幼稚園に行き始めたばかりで、風邪をひかないのは無理な話と思います。
予防薬を処方するかは、「発作の重症度」と「頻度」に応じて開始するものですので、現在の時点で長期管理を開始すべきかどうかは、主治医の先生とよく相談して頂くのが良いかと思います(例えば、毎週のように感染に関係なく喘鳴がある場合は何らかの定期治療を始めるでしょうし、入院を要するような大きな発作が起こったことのある方は、ステロイドの吸入などがすすめられる場合が多いかと思います)。
今後も、有症状時には喘鳴の有無などを確認してもらい、治療方針の相談をなされるのがよいかと思います。
(小児科 内藤)
喘息診断を受けましたが、日によって医師が変わるような小児科だったり、小児科専門医ではなくとも小児科を掲げている先生のもとで治療を続けてきました。 医師によって治療方針が異なり、戸惑っています。パルミコート吸入を1日1回に減らされたり、2回に増やされたり…。そんなに頻繁に変更しても差し支えないのでしょうか?
医師によって治療方針が異なることがあるとのことですが、戸惑われるのも当然と思います。
外来で長期管理をする場合は、可能な限り同じ小児科医に受診できる病院をおすすめします。
パルミコート吸入の量の変更についてですが、長期管理では3か月から落ち着いていたら減量をこころみるとガイドライン(専門家でつくる治療の指針のようなもの)では推奨されています。必ずしもその通りにする必要はないのですが、毎週のように増やしたり減らしたりする薬ではなく、数か月単位で効果を判定して増減を考える薬剤であると思っております。
(小児科 内藤)