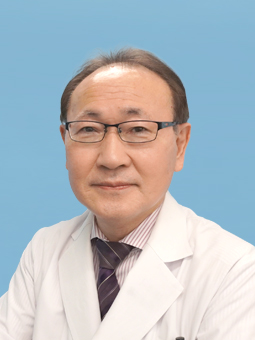病理診断科のご案内
特長
病理診断科で実施している日常業務は、①生検・手術検体の病理組織診断、②術中迅速診断、③細胞診断、④病理解剖の4つの業務です。3名の常勤病理医と2名の非常勤病理医で診断にあたっています。また、臨床検査技師は8名で検体から顕微鏡標本の作成を行っています。うち6名の細胞検査士は細胞診標本のスクリーニングをし、異形、悪性の標本をピックアップし、医師とともに診断にかかわります。
病理診断には常に正確さと迅速性が求められ、臨床からのニーズに合った内容の報告はもちろんのこと、最近は分子標的治療薬の適応、選択のための診断も要求されることが多くなっています。病理診断にあたっては臨床医からの詳細な情報が得られ、診断の目的が明確であればより詳細で目的に合った病理診断が可能になります。
病理解剖については、心肺停止状態で救急搬送され亡くなった症例、予期せぬ病態で亡くなった症例、臨床診断が困難だった症例などがあり、その病態、診断を明らかにするために実施しています。それらの多くはCPC(臨床病理検討会)の場で議論され、後の診療のために役立てられています。
学会認定施設
日本病理学会:研修認定施設B
日本臨床細胞学会:認定施設 / 教育研修施設
がんと病理診断
ヒトのからだは多数の細胞が集まってできており、それぞれの細胞は周囲の細胞と協調しながら一定の働きをしています。その一部が協調を無視して勝手に増えてしまう細胞(がん細胞)に変化し、本来あるべき場所ではないところにも拡がってしまう(浸潤、転移)のが、“がん”という病気です。
がんの診断を確定するためには、病変の部位に“がん細胞”が存在することを顕微鏡下で確認する必要があります。これは病理組織診断と呼ばれている医行為であり、がんの診断・治療のさまざまな場面にかかわっています。がんの診療にはなくてはならないものです。
がん治療前の病理診断
がんの診断を確定するために、がんが疑われている病変から一部組織を採って(生検といいます)顕微鏡標本(組織標本)を作製し、組織診断(がんであるかどうか、どのような種類のがんであるか、悪性の度合いはどの程度かなど)が行われます。特殊な染色や遺伝子検査を実施し、ある種の分子標的治療を含めた抗がん剤治療が有効かどうかを調べる場合もあります。生検のやり方としては、内視鏡検査で消化管のがん(食道がん、胃がん、大腸がん)や肺がんの一部をつまみ取ってきたり、針を刺して乳がんや前立腺がん、肝がんの一部を採ってきたりする方法があります。
がん細胞を顕微鏡下で確認する方法には、細胞診もあります。痰(たん)の中の肺がん細胞や尿の中の膀胱がん細胞を見つけるのは細胞診であり、子宮頚部がんの診断のために子宮膣部を擦り取って診るのも細胞診です。がん細胞が認められれば、さらに病変部の生検を行って確認します。乳がんでは、生検同様、病変部に針を刺して乳がん細胞を吸引採取する細胞診も行われます。膵がんや胆道がんなどでは、膵液や胆汁中のがん細胞をみつける細胞診が診断に有用です。
生検による組織診断と細胞診とでは、がん細胞の採れ方や顕微鏡標本の作り方が異なりますが、がんが発生した臓器や状況に応じて一方もしくは両方を行うことで、治療前のがんの診断が確定されます。
がん手術中の病理診断
がんの手術中、リンパ節などへの転移の有無や、臓器をからだから切り離したところ(断端)にがんが存在していないこと(手術で病変がとり切れていること)などを、その部位の組織標本を作製して確認することが行われ、術中迅速組織診断と呼ばれています。組織を凍らせて短時間で顕微鏡標本を作製し、連絡を受けてから20分以内には病理診断結果を報告しています。
胃がんや卵巣がんの手術などでは、おなかの中(腹腔内)にたまった液体(腹水)の中にがん細胞が散らばっていないかを確認するための迅速細胞診も行われます。
手術や内視鏡で切除されたがんの病理診断
手術で切除されたがんは、切除された臓器の中での病変の部位や病変の形・大きさを肉眼的に確認・記録した後、必要な部位から組織標本を作製して、がんの種類や広がり、リンパ管や血管内にがん細胞が入り込んでいるなど転移の可能性を高める要因の有無、手術でとりきれているかどうか、同時に切除されたリンパ節への転移の有無、などを最終的に確認します。それらに基づいて最終的ながんの進行度(ステージング)が決定されます。
消化管のがんなどでは、がん病巣を内視鏡で切除することが可能な場合がありますが、手術で切除されたものと同様に病理診断がなされます。がん病巣を最小限に切除しているため、切除されたものを細かく切ってすべてを組織標本とし、がんがとりきれているかどうかを十分に確認することが必要となります。
これら病理診断の結果は、がん切除後の追加治療の必要性などを決める重要な指針となります。生検のところで述べた特殊染色や遺伝子検査を、この段階で行う場合もあります。認定医が読影しています。
がん治療後の病理診断
手術後のがん再発の有無や放射線・抗がん剤による治療効果などを確認するために、治療後にも生検や細胞診が行われ、それらに対する病理診断がなされます。
必要に応じて、保存されている標本を用いて特殊染色や遺伝子検査が追加される場合もあります。
実績
病理診断・解剖実績
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
| 病理組織診断 術中迅速診断を含む |
4,418 件 | 5,257 件 | 5,285 件 | 4,929 件 | 4,975 件 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 術中迅速診断 | 216 件 | 234 件 | 243 件 | 227 件 | 207 件 | |
| 細胞診断 | 8,484 件 | 9,107 件 | 8,984 件 | 9,226 件 | 9,038 件 | |
| 病理解剖 (内科例) |
12 件 (10 件) |
14 件 (13 件) |
4 件 (4 件) |
10 件 (9 件) |
10 件 (9 件) |
|