リハビリテーション科のご案内
特長
リハビリテーション科では、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士がチームで患者さんの症状に合わせ必要に応じて急性期からリハビリテーションを提供しています。経験豊富なスタッフが多く、しっかりとしたリスクマネージメントのもとで安全にリハビリテーションが実施できるように努めています。
対象疾患は脳神経外科、整形外科、循環器科内科を中心に多岐に渡ります。また、毎朝スタッフでミーティングを行い、患者さんの情報共有や退院の方向性を検討しています。


スタッフ紹介
医師 / Doctor
太田 剛(おおた つよし)
| 役職 | 主任部長 整形外科 部長 |
||
|---|---|---|---|
| 診療科 | リハビリテーション科 | ||
| 専門分野 | 手の外科 上肢一般 末梢神経障害 |
||
| 資格・認定 | 日本専門医機構:整形外科専門医 日本整形外科学会:指導医 日本リハビリテーション医学会:リハビリテーション科専門医 / 指導医 日本手外科学会:手外科専門医 / 指導医 東京科学大学医学部:臨床准教授 |
||
| メッセージ | 高齢化にともない、リハビリテーションの重要性はますます高まっています。 当院は急性期のリハビリテーションとして、術前からリハビリ介入を行い、早期のADL復帰を目指した治療を行っています。 |
||
半田 和佳(はんだ わか)
| 役職 | 医員 | ||
|---|---|---|---|
| 診療科 | リハビリテーション科 | ||
| 専門分野 | |||
| 資格・認定 | 日本専門医機構:整形外科専門医 | ||
技士 / Therapist
| 理学療法士 | 18 名 |
|---|---|
| 作業療法士 | 5 名 |
| 言語聴覚士 | 3 名 |
施設基準・認定資格
施設基準
- 運動器疾患リハビリテーション(Ⅰ)
- 脳血管疾患等リハビリテーション(Ⅰ)
- 呼吸器疾患リハビリテーション(Ⅰ)
- 心大血管疾患リハビリテーション(Ⅰ)
- がん患者リハビリテーション

認定資格
| 認定資格名称 | 人数 |
| 3学会合同呼吸療法認定士 | 5 名 |
|---|---|
| 認定理学療法士 (呼吸器) |
2 名 |
| 認定理学療法士 (運動器) |
2 名 |
| 認定理学療法士 (脳卒中) |
1 名 |
| 認定理学療法士 (地域理学療法) |
1 名 |
| 認定理学療法士 (代謝) |
2 名 |
| 認定資格名称 | 人数 |
| 日本糖尿病療養指導士 | 1 名 |
|---|---|
| 認定理学療法士 (循環) |
2 名 |
| 認定理学療法士 (スポーツ) |
1 名 |
| 心臓リハビリテーション指導士 | 5 名 |
| 介護支援専門員 | 1 名 |
| 心不全療法指導士 | 2 名 |
各部門紹介
理学療法
理学療法は、運動療法や物理療法を用いて、病気やけがによって失われた機能の起きる・座る・立つ・歩くなどの基本的な動作能力の回復を促し、日常生活や社会復帰までサポートしていきます。
当院では、脊椎疾患の方が非常に多く、リハビリテーションの対象も脊柱管狭窄症や腰椎変性すべり症などの手術後の患者さんが多いのが特徴です。また、午前中には1名の理学療法士が訪問リハビリテーションを実施しています。

作業療法
作業療法の作業とは、人が生活するうえで行う全ての活動(食事をする、仕事をする、本を読むetc)を意味しています。そのため作業療法では、機能的な改善はもちろん、患者さんにとって大切な作業をどのようにすれば行いやすくなるかを共に考え、繰り返し練習することで、患者さんの日常生活(食事、着替え、入浴etc)および社会生活(主婦としての家事etc)への復帰をサポートしていきます。
当院では主に脳神経外科、整形外科(頚椎疾患、手外科)に関わることが多いですが、その他に心不全や廃用症候群に関わることもあります。
入院患者さんの内訳は、脳神経外科が6割、整形外科が2割、その他2割となっています。

言語療法
言語療法では主にコミュニケーションや飲み込みに障害のある方に対して言語機能や摂食・嚥下機能の改善を目的としたサポートを行っています。
脳卒中後には失語症や構音障害などのコミュニケーション障害を生じることがあり、そのような患者さんに対して言語評価、訓練を行います。また、毎週水曜に歯科医師と看護師と共に摂食・嚥下機能の評価(外部評価、ミールラウンド、VE、VF)を実施しており、その結果に応じて必要な患者さんに嚥下訓練を実施しています。

心臓リハビリテーション
当院では医師、看護師、理学療法士、作業療法士、臨床検査技師、管理栄養士などとの連携のもと、他職種による包括的リハビリテーションを行っております。
当科では心筋梗塞や心不全の患者さんの早期離床・治療のための心臓リハビリは入院直後からベッドサイドで開始しています。また、退院後の患者さんに対して外来での心臓リハビリテーションも実施しております。外来での心臓リハビリテーションの流れや効果については下記をご参照下さい。

当院では心肺運動負荷試験(CPX)に基づく適切な運動処方により、心血管疾患の再発予防・自覚症状の改善ならびにQOLの改善を目指し、患者さんとともに治療を進めています。心肺運動負荷試験(CPX)については下記をご参照ください。
心臓リハビリテーションについて
外来リハビリテーションの流れ
| STEP 1 | メディカルチェック(体調や血圧などの確認) |
|---|---|
| STEP 2 | モニター心電図の装着 |
| STEP 3 | 1. ストレッチ:10分 2. 筋力強化トレーニング:10~15分 3. 有酸素運動(自転車エルゴメータ):20~30分 |



心臓リハビリテーションの効果
運動能力・体力が向上します。
運動能力が向上すると、日常生活における息切れや狭心痛などの諸症状が改善します。
運動能力の向上効果は性・年齢に関わらず認められます。また、もともとの運動能力が低いほど効果が大きいものとなります。ご高齢の方でも運動療法は可能です。
骨格筋機能が改善します。
体力が向上する第一の要因です。運動療法を行うと、筋肉の量が増え、質も良くなり、楽に動けるようになります。そのため、同じ動作や運動をしても心臓への負担は少なくなります。
自律神経が安定します。
心臓病では自律神経活性が乱れます。これは不整脈や場合によっては突然死とも関係します。症状としては、脈が早くなったり、ドキドキしたりします。
また、手足の血管が細くなって疲れやすくなったり、血栓の元になる細胞を活発にさせて血栓塞栓症の原因を作ります。
運動療法を行うと自律神経が安定して、動悸や血栓の心配を減らすことができます。
冠危険因子が改善します。
運動療法は血圧、中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール、総コレステロール、血糖値、体重などが異常である場合、これらを改善させ、冠動脈硬化症の再発予防に有効です。食事療法を併用すると、さらに有効です。
末梢循環が改善します。
心臓病の人の手足が冷たいのは、血管が硬くて広がらないことが原因です。
運動療法を行うと血管が広がりやすくなり、手足が温かくなります。体のすみずみまで新鮮な血液を運ぶことができるようになるため、筋肉への栄養補給もスムーズになります。これも運動療法によって心臓病の症状がとれる1つの要因です。
生活の質が改善します。
運動療法は“生活の質”を改善します。生活の質とはやる気、希望、日常生活の快適さなどのことです。
ある研究では85%の患者さんが「運動療法によって仕事への満足度、家庭生活、社会参加などが改善した」と報告されています。
精神面においても良好な結果があります。
心疾患患者さんの約40%が精神的に不安定(うつ状態)になると言われています。精神的なストレスは冠動脈疾患患者さんの状態を悪化させ、時には動脈硬化病変を不安定にします。運動療法は不安定な精神状態を改善してくれます。とくに集団で心臓リハビリテーションを行うと効果が高いと言われ、うつ状態が改善するだけで寿命が延びるとも言われています。
生命予後が改善します。
研究により6か月間の心臓リハビリにより、心筋梗塞の患者さんの3年間の死亡率が52%も減少したことを報告しています。
また、慢性心不全に運動療法を単独で行なった研究では生命予後改善効果と再入院率の減少をもたらすことが明らかになっております。
このように心臓リハビリは、単に自宅退院、ADL(日常生活活動)の自立や復職にあるのみではなく、再発防止や生命予後の延長までを目指すものです。
CPXについて
心臓、肺だけでなく筋肉を含めて、運動耐容能(体力)を評価する検査です。
「無理しない範囲で運動してください。」と言われたことがある心臓病の患者さんは多いと思います。このCPX検査の主な目的“無理しない範囲”を明確にすることです。心臓病の方々に運動処方をするには、この検査は必須であると言っても過言ではありません。
心電図、血圧、呼吸中の酸素、二酸化炭素の濃度を測定しながら、自転車をこいでもらいます。色々なモニターを装着し医師の監視下で行われるので、非常に安全に行えます。苦しいとか苦しくないとか、そういった主観的な評価で運動を処方することも可能ですが、科学的な裏付けは治療の効率をあげる可能性があります。
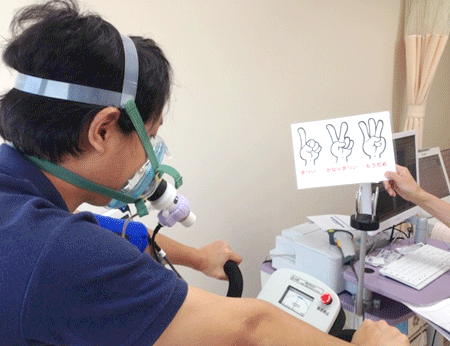

運動耐用能の評価にはさまざまな指標が用いられますが、重要なものは嫌気性代謝閾値(anaerobic threshold :AT)と最大酸素摂取量(Peak VO2あるいはVO2 max)です。
AT (anaerobic threshold)とは?
人間は酸素を吸って二酸化炭素を吐くという呼吸をしています。軽い運動をしている分には酸素の量と吐き出した二酸化炭素の量は一定の割合となります。酸素が十分にとりこまれ、心臓に負担がかからない運動量です(有酸素運動)。
しかし、運動量が増加すると筋肉に乳酸がたまります。その乳酸を分解するために代謝系が働いて、二酸化炭素を吐く量が増えます(無酸素運動)。
このように酸素が不足した運動を長く続けると心臓や全身に負担がかかります。また、心臓病の方は不整脈が出現しやすいと研究で分かっています。
ATとはこの有酸素運動が無酸素運動に切り替わるポイントを言います。心臓リハビリをしていただくときの運動強度はきついと身体に負担となり、逆に軽すぎると十分な効果が出ないことがあります。そこで、このATレベルの運動量を知ることによって、最も負担が少なくて効率的にトレーニングを行うことが可能になります。
最大酸素摂取量(VO2 max)とは?
最大酸素摂取量(VO2 max)=最大心拍出量×最大酸素利用能
式が表すとおり、心肺機能と呼吸機能を反映します。心肺機能から見た最大の運動能力を示します。
心不全の程度と予後を表す重要な指標になります。
CPX検査では、ここで示したほかにも色々なことが解ります。この検査をしっかりと施行・解析して、心臓リハビリテーションを実施しています。
【患者さんへ】
運動療法に興味のある方、運動したいと思っているけど心臓の病気が心配で運動ができない方など、一度ご連絡頂くか、当院のリハビリテーション室までお越しください。心臓リハビリスタッフがお話を伺います。当院に通院されていない方でも可能です。
お気軽にリハビリテーション室にご相談下さい。
【医療関係の方へ】
当院の心臓リハビリテーションでは、他院で入院治療やカテーテル治療、心大血管手術を受けられた患者さんでも、外来心臓リハビリテーションを行っていただくことができます。
地域医療連携室までご連絡ください。
| 連絡先 | 地域医療連携室(医療機関専用) 平日 9:00~17:00 TEL:048-253-8136 |
|---|